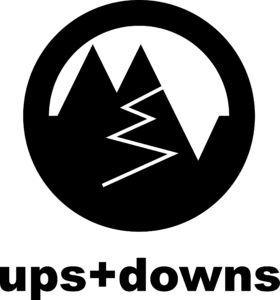登山用品ショップ ups+downs のスタッフブログ『山あり谷あり』です。
ファンナップネイチャーが主催する机上での雪山登山講習の第三回目(最終回)に受講してきました。
教わった内容をメモ書き程度になりますが、紹介させて頂きます。

講座名:雪山のリスク管理
開催場所:渋谷区文化総合センター大和田
(渋谷駅から徒歩約5分)
開催時間:19時~20時20分
費用:1000円(各種キャッシュレス対応可)
【リンク】FUNUP Nature
まず、これまでの講習のトピック
★冷えの原因となるので汗はかかないようにする
服をまめに脱ぎ着する
ペースを落とす
★思った以上に足が冷える
雪山用登山靴と靴下は雪山用がいい
★靴とアイゼンは相性がある
アイゼン購入時には靴を持参する
(足先が狭くて装着できないなど)
店で買うと高いのでAmazonで買う予定ですが・・・
★手袋は重ね着用(3レイヤー)推奨
★インナー手袋で雪を触らない雪に付けない
★手袋や靴下は予備持参。濡れ→冷え→凍傷になる
★雪目対策を万全に
雪山ではサングラスまたはゴーグルを常時着用!
その時は平気でも、後から症状が出る
★アイゼンは傾斜場用、ワカン&スノーシューは平坦で雪深いところ用
★冬山登山は食欲がなくなりやすい、厚着してるので食事が面倒
夏よりエネルギーを使うので意識して食事をすること
★天候は7日周期で、7日に一度好天の日がある
できればその日を狙う
雪山=冬山ではない
・降雪期、残雪期など様々な状況がある
リスク1:傷病(凍傷/低体温症/雪目など)
凍傷とは?
体の水分が凍り、皮膚や組織が損傷すること
指先や耳、鼻など血流が少ない部分で起こりやすい
低体温症とは?
体温が35℃を下回る危険な状況
震え、意識の低下などの症状
命を落とすこともあり
夏でもなる
凍傷、低体温症の原因
低気温、風
2024年1月4日の燕岳は-18℃
森林限界より上では木がないので風が強い
肌の露出を避ける
服の中の暖かい空気を逃がさないように首、手首、腰、脚組などのウエア開口部はしっかり塞ぐ
冬用ウエアの開口部を締めるヒモの位置を覚えておく
ゲイターやバラクラバ、シェルのフードも有効
血流の確保
靴ヒモは甲はゆるめに締める
足首部は適切に締める
喫煙は末端血管が収縮するので避ける
脱水は血液の粘性が増し、血流悪化の要因となる
濡れ
濡れは雨のほか、汗も要因となる
<身体>
汗をかかないよう着すぎないこと
小まめな衣服調整
ペースを落とす
ドライレイヤーを着る
ヒートテックや綿素材のものは汗を含みやすいので避ける
<手>
グローブは外さない→雪に付けないため
グローブをしたままアイゼンなどの装備を扱える練習が必要
スマホはタッチペンを使う
<足>
暖かい場所では靴内で汗をかく→濡れの原因
電車移動時などは別な靴を履く。
その靴は駅のコインロッカーなどに預ける
または電車では靴を脱ぐ、薄手の靴下に履き替えるなどの対策をする
<その他>
帽子にも気を付ける
バンダナなど頭頂部が開いているのも有効
疲労、エネルギー不足
冬山は強風が発生しやすい
強風を受けるストレスによる疲労
楽しく会話することは疲労軽減につながる
雪上での作業が面倒&食べたくなくなるエネルギー不足
体温を保つようエネルギーを意識して補給すること
震えがない場合は助けを呼ぶ
震えるエネルギーもなくなっている状態
会話が不明瞭、歩行障害ありの場合も
深部体温は測定できないので、行動や意識から見分けること
日焼け/雪目
雪面反射で通常より強い紫外線を浴びる
(対策)
日焼け止め、リップクリーム、サングラス、ゴーグル
場合によってバスやロープウェイでも対策すること
ゴーグルはシールドがピンクのものが地面の凹凸を視認しやすい
風に舞った氷から目を守るため、曇りでもサングラス着用推奨
低体温症の手当方法
隔離■雨・風からの隔離(ツェルト、シート、かまくら)
保温■防寒着、シェラフ、ザック、マット等による保温
加熱■ボトルで湯たんぽ、胸や脇下を温める
リスク2:けが
アイゼンで岩の上を歩くと滑りやすい
滑落に気を付ける
リスク3:雪崩
雪崩はいつどこで起こるかが分からない
雪崩の発生しずらい時間に行動する「早出早着」の励行
リスク4:天候
2月後半(春一番)、高山でも雨、みぞれになる→濡れの原因
低気圧通過中は雨、通過後に気温低下が発生し、濡れ→低体温症に発展する
春先、晩秋は晴天の予報でも、念のため雪装備を携行のこと
行ってみたら雪があったなどある。
「小まめに脱ぎ着する」
「意識して食事を取る」
「アイゼンは水平に着く」
雪山登山中、講習で習ったことが何気に役立ちました。
皆さんにも参考になれば幸いです。